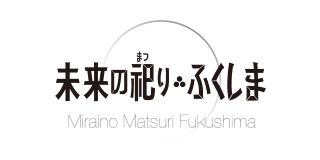「未来の祀り・ふくしま 2015」開催まで、あと2か月ほどになってきました。
「震災」「鎮魂」「芸能」「祀り」……これらのキーワードがどう結びついてくるのか?
イベント本番にむけた予習的フィールドワークにお付き合いください。(及川俊哉)
「未来の祀り」や「未来芸能」といった言葉は、みなさん聞きなれないものだと思います。
今回は「未来の祀り」「未来芸能」をより楽しんでもらえるように、この言葉について説明していきたいと思います。
未来芸能がめざしているもの、その目的を理解していただくためには、
古代人のものの考え方を理解しておく必要があると思います。
古代人がおこなっていた「古代芸能」は、「鎮魂」や「ご神事」など、
現代人の目には異なるジャンルだと思われるものが、ひとつにまとめられたものでした。
ひとつ例をあげてみます。
人間の体は、腕や足や内臓や顔など、さまざまな部分に分かれています。
しかし、もともとはお母さんのおなかの中にある一つの卵細胞でした。
たった一つの細胞が、成長するにしたがって、手や足に分かれていったのです。
現代人は「芸能」というと、楽しい娯楽だと思い、
「鎮魂」というとお寺でやるお葬式に似たもの、などというように、
まったく別のジャンルのおこないだと思っていますが、
歴史をさかのぼっていくと(……人間の体がさかのぼると一つの細胞だったことと同様に)、
「古代芸能」も一つのおこないが多くの意味を持つものだったのです。
つまり、古代人が歌や踊りを見るときは、たのしくゆかいな気分になりながら、
一方で、これは亡くなった人の魂をなぐさめるためにやっているんだな、とか、
神様にささげるためにやっているんだな、ということが、わかっていたのです。
ひとことでいうと、古代人にとっては歌や踊りも「祈り」の行為だったのです。
また、そういう気持ちをもつことが、古代人には真剣に必要なことでした。
現代のように科学が発達していない時代には、
病気や災害にあった時には、祈るしかありませんでした。
問題の解決方法がないことに対して、祈るという行為や思いは、
いまのわたしたちには想像できないほど、真剣なものだったと思います。
近代に入ってからは、科学が発達し、たくさんの病気の治療法が見つかり、
土木工事などで、災害も克服されるようになりました。
これは、たいへんすばらしいことです。
ただ、科学の発展とともに、古代人の「祈り」の考え方は、
古くさいものとして忘れさられたように思います。
「祈る」という行為も、形式化してしまったように思います。
これは残念なことです。
(福島稲荷神社境内の樹木)
ところが、東日本大震災をきっかけに、現代の科学ではまだまだ解決できない問題が、
ふたたびたくさん現れてきました。
もちろん、科学的物理的に解決しなければならない問題は、いま専門家の方々が、
一生懸命努力して取り組んでいらっしゃいます。
そして、将来的には、科学的な方法でさまざまな問題も解決されていくでしょう。
ただ、それにはどうやら長い長い時間がかかりそうです。
そのあいだ、わたしたちは、どうやって心を折らずに、待っていればいいのでしょうか。
わたしたちはこの点に、古代人の祈りの感覚が役に立ってくれそうだと思うのです。
古代の人々は病気や災害に対して、祈ることしかできませんでした。
しかし、祈りながら、現状を「より良くしたい、より良くなろう」という気持ちは、
心を折らずに、持ち続けていたのだと思います。
その結果として、いまのわたしたちの社会があるわけです。
さまざまな困難にくじけそうになりながらも、あきらめなかった人たちがいて、
その人たちの「祈りのバトン」が、いまのわれわれにつながっているわけです。
また、そのような祈りを、長く続けていくために、
「芸能」のような楽しみのある手段も、のこしておいてくれました。
こうした古代人の考え方に、いま、学ぶ点が多いのではないかと思います。
「未来芸能」と言ったとき、イメージしていただきたいのは、
未来の次の世代につながる「祈りのバトン」です。
おこなうことは創作芸能ですが、「芸能」がそのまま「祈り」だった古代人の考え方に学んでいます。
さて、このような古代人の考え方を、詳しく調べておいてくれたのが、
民俗学者の折口信夫です。
次回からはまた、折口信夫の書いた本を参考にしていきたいと思います。